 |
 |
自宅は“使える財産” セカンドライフの収入源 船井財産コンサルタンツ・蓮見正純さん提案 |
 |
 |
|
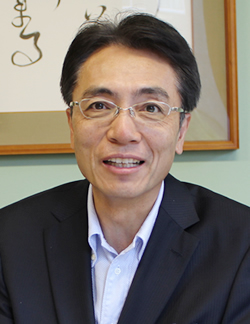
蓮見正純さん |
安心できる定年後のセカンドライフには一体、いくら必要なのか—。この漠然とした疑問点に対して、公認会計士で(株)船井財産コンサルタンツ(港区)社長の蓮見正純さん(55)は、セカンドライフの収入源として自宅の活用を提案している。
3月11日の東日本大震災で未曽有の災害に直面して以来、「生活は自分たちで守らなければ」という意識が高まっている。しかし、これから定年を迎える人たちにとって、年金制度の先細りや不動産価格・株価の低迷、ゼロ金利の長期継続などがセカンドライフを送る際のリスクとなっている。
このため蓮見さんは「住宅を消費財ではなく財産の一部として捉える人は、自宅に対する見直しがすごく大切になってくる」と話す。自宅を“使える財産”あるいは“果実を得る収入源”として捉え、賃貸や売却などで豊かなセカンドライフの資金源にすることを検討すべきだという。
生命保険センターの生活保障に関するアンケート調査(60代が回答)によると、夫婦2人で老後の生活を送る上で必要と思われる毎月の生活費は日常生活費で22万7000円。ただし、経済的にゆとりある生活を送るためにはさらに13万6000円が必要と考えている。合計で36万3000円になる。
ところが、総務省の全国消費実態調査によると、65歳以上の高齢者世帯の毎月の平均収入(給与収入、諸経費控除後の農林漁業収入・事業収入、家賃・地代の年間収入、年金受取額、利子配当金などの合計額)は37万円。消費支出は25万円となっている。収入と支出の差、12万円がどうなっているのかは分からないが、“長生きリスク”に備えるための貯蓄に一部が回っている可能性もある。
“長生きリスク”に対する不安を和らげるための、経済的基盤として考えられるのが自宅の活用だ。「子どもたちが独立して夫婦2人になったら2人住まいに適した規模の家に引っ越し、家を貸すか売却するなど検討してみては。その資金を収入源にして豊かなセカンドライフを過ごすのも一つの方法」と蓮見さん。
特に自宅を収入源とする効果が大きいのが東京。不動産価額が高い東京では、個人資産に占める自宅など不動産の比率が高く、63%=総務省全国消費実態調査=を占める。
不動産の公示地価(内閣府国民経済計算、国土交通省地価公示)は91年をピークに下がり続け、09年までに約53%減と半分以下になっている。これに伴い、不動産資産残高もおよそ半減している。少子化の影響で、今後も地価下落は続くと予想する向きが多い。このまま自宅を資産として見直さずにいると、資産の目減りは避けられそうもない、ということも考えておくべきだ。
65歳以上の高齢者人口は全国約2900万人(09年、総務省人口統計)で全人口の約23%。50歳以上となると約5500万人、約43%に達する。「財産管理は幸せな人生を支える土台。今後、高齢者が増えていく中で、その人たちが生き生きと生活すると世の中が明るくなる」と蓮見さん。財産や経済基盤を保っていくことが安心して老後を送ることに欠かせなくなっている。 |
| (株)船井財産コンサルタンツ TEL.03・6439・5800 |
|
|  |
|